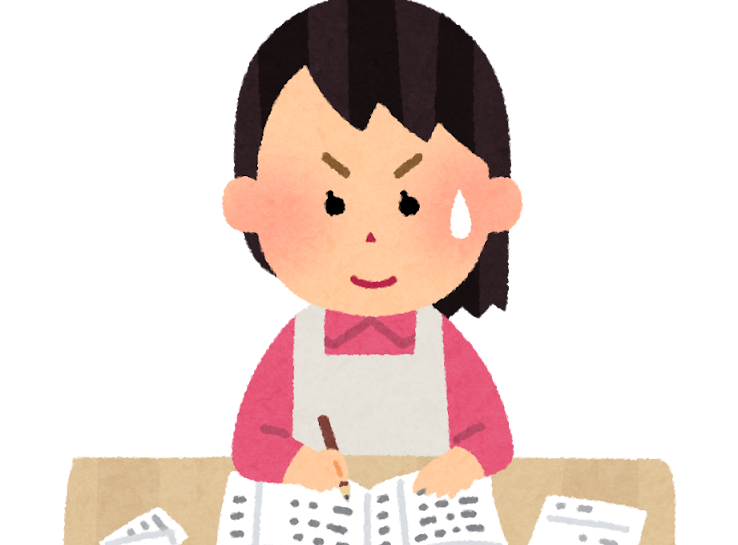明けましておめでとうございます。
今年も、本ブログをよろしくお願いいたします。
みなさま、良いお正月は過ごせたでしょうか。
私は例年通り、実家で家族と過ごしました。
特段、何も変わらず12/31の夕方、妻が仕事が終わってから実家に帰省し、夕ご飯と年越しそばを食べて、近所のお寺に除夜の鐘を月に行き、一泊して、初詣に出かけ、おせちを食べて終わりました。
その様子をいくつか、写真付きでご紹介したいと思います。
我が家のおせち

毎年、妻が作っている恒例のおせちになります。
なかなか自作する家庭も少なくなってきたかもしれませんが、我が家はなんだかんだあって今も妻が年末からコツコツ自作してくれています。
これがあるので、実家の父も私も「お正月らしさ」を感じることができていると思います。
ちなみに、最初は一から頑張って色々手作りしてくれていましたが、側から見ているとだんだん効率が良くなってきて、出来合いのもので済ませたりして時短で頑張って作成してくれています。
元旦の朝
私の実家は、結構山の上の方にありますので、朝晩は気温が低くなります。
私もそこで育ったのですが、長らく離れているのでその感じを忘れていました。
初詣に行く前に外に出ると、すっかり日陰部分は霜が降りていました。


そして、ご近所さんにご挨拶に行くと、家の入り口に芋が干してあり、干し芋を作っているとのことでした。
田舎ならではの風景ですねー。

初詣(パート2)
初詣は、地元の神社に行きます。
大体2箇所行くのですが、2箇所目が「山の上」にある神社でかなり穴場なのでレポートしたいと思います。

この階段を登っていきます。
以前何度も数えたんですが、一体何段あったか忘れてしまいました。
多分この登り階段を登ると、一旦平坦があってまた同じこれぐらいの階段があります。
多分500段くらいあった記憶があります。

子供達は駆け上がっていってしまい、あっという間に妻と二人取り残されてしまいました・・・

周囲は樹齢100年を超えていると思われる大型の樹木が生い茂っています。
なぜわざわざしんどいのにここにお参りするかというと、昔からあるのと、お正月のこの時しか一年の中で来ないからです。
一応毎年お参りに来ているのですが、年々お参りする人が減っていて(多分高齢化が原因)山道の階段も荒れてきている気がします。
なので、せめて年に1回はお参りしたいと考えています。

頂上にある神社です。
昔の人はなぜ、こんな山の上に神社を、しかもどうやって作ったのでしょうか?
途中に石垣がいくつかあったので、昔はこの辺りの山の中にも集落があったのかもしれません。

神じゃ内部はシンプルで常にオープンスタイルです。
この奥の部分に奥の院があるのですが、私は入ったことがないのでどうなっているかわかりません。

山頂の神社からは、遠くまで景色が見渡せます。

朝で天気も快晴であったため、木漏れ日が見えてとても神秘的な空間でした。
2025年もブログを始め、色々と0→1で始めたことが軌道に乗るよう頑張っていきたいともいます。
今年もよろしくお願いします。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました😃